高齢期に入ると、医療費の負担は多くの方にとって大きな懸念事項となります。しかし、日本には医療費の負担を軽減するための様々な制度が整備されています。これらの制度を賢く活用することで、安心して医療サービスを受け、経済的な不安を減らすことが可能です。この記事では、特に高齢者の方が活用すべき主要な医療費軽減制度を5つご紹介し、その内容と活用のポイントを詳しく解説いたします。所得や年齢などの条件に合わせて、ご自身に最適な制度を組み合わせ、上手に活用していきましょう。
1. 高額療養費制度を理解する
高額療養費制度は、ひと月(月の初めから終わりまで)に医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、所得や年齢に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。この制度は、医療費が高額になった際に家計を圧迫しないよう設計されています。
上限額は、所得区分や年齢によって細かく設定されています。例えば、70歳以上75歳未満の方の場合、外来と入院を合算して計算する「外来・入院一体型」の上限か、外来のみに適用される「外来別」の上限かによって、払い戻しの対象となる金額が変わってきます。申請から払い戻しまでには通常2~3か月程度の期間がかかりますので、高額な医療費を支払った際は忘れずに申請しましょう。
|
区分 |
ひと月上限額(世帯ごと) |
外来(個人ごと) |
|---|---|---|
|
現役並み所得者Ⅲ |
|
― |
|
現役並み所得者Ⅰ~Ⅱ |
|
― |
|
一般(年収156~370万円) |
|
[年] |
|
住民税非課税世帯 |
|
|
2. 後期高齢者医療制度の活用
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(または65歳から74歳で一定の障がいがあると認定された方)が加入する公的な医療保険制度です。この制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が原則1割となっていますが、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。
この制度の財源は、公費が約5割、現役世代からの支援金が約4割、そして被保険者からの保険料が約1割で構成されています。所得に応じて2割負担となる方には、外来の自己負担増を月額3,000円以内に抑えるといった配慮措置が講じられています。
また、「限度額適用認定証」を事前に取得し、医療機関の窓口で提示することで、支払う医療費を最初から上限額までに抑えることができます。これにより、一時的な高額な窓口負担を避けることが可能になります。
|
負担割合区分 |
判定基準 |
|---|---|
|
1割 |
上記の2割・3割に該当しない場合 |
|
2割 |
(1)世帯内に課税所得28万円以上の方がいる、かつ(2)年金収入とその他の所得の合計が単身で200万円以上、または複数世帯で320万円以上の場合 |
|
3割 |
世帯の所得要件が「現役並み所得者」に該当する場合 |
3. 医療費控除で税負担を軽減する
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に実際に支払った医療費(保険金などで補填された金額を除く)が、一定の金額を超えた場合に、その超過分を所得から控除できる制度です。これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
控除の対象となる金額は、「10万円」または「総所得金額の5%」のいずれか低い方を超えた分です。例えば、年金生活者などで総所得金額が200万円未満の場合、10万円に満たない医療費でも5%基準が適用され、控除の対象となることがあります。
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。医療費控除の明細書を作成し、領収書を保管しておくことが重要です。過去5年間の医療費についても遡って申告が可能ですので、もし申告を忘れていた年があれば確認してみましょう。
4. 高額介護合算療養費制度の活用
高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している方が対象となる制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得区分別に設定された年額上限を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。
この制度は世帯単位で計算され、医療保険と介護保険それぞれの保険者から支給されます。特に70歳以上の世帯には、一般の世帯よりも低めの限度額が適用されるため、より手厚い支援が受けられます。
|
所得区分 |
70歳以上世帯限度額(年額) |
|---|---|
|
現役並みⅢ |
|
|
現役並みⅠ~Ⅱ |
/ |
|
一般(標報26万円以下) |
|
|
住民税非課税Ⅱ |
|
|
住民税非課税Ⅰ |
|
医療と介護の両方に高額な費用がかかっている場合は、この制度を忘れずに申請することで、大幅な負担軽減につながります。
5. 自治体独自の医療費助成制度を知る
国が定める制度のほかに、お住まいの市区町村が独自に医療費の助成を行っている場合があります。これらの自治体独自の制度は、所得や年齢、介護度などを要件としており、受給者証を医療機関の窓口で提示することで、自己負担が無料になったり、低額になったりするものです。
助成の対象となる範囲や金額は自治体によって様々です。医療費の償還払い(一度支払った医療費が後から払い戻される)形式の助成もあります。
例えば、特定の年齢層(67歳~70歳未満など)への助成や、障がい者医療助成、ひとり親家庭への助成などが挙げられます。ご自身が居住する自治体のウェブサイトを確認したり、窓口に問い合わせたりして、利用できる制度がないか積極的に情報収集することをおすすめします。
まとめと制度活用のポイント
高齢者の医療費負担を軽減するための主要な制度は多岐にわたりますが、これらは単独で利用するだけでなく、組み合わせて活用することが可能です。
まず、医療費が高額になることが予想される場合や、すでに高額な医療費を支払っている場合は、「高額療養費制度」や「後期高齢者医療制度」の限度額適用認定証を早めに取得しましょう。これにより、窓口での支払いを上限額までに抑え、一時的な負担を軽減できます。
次に、1年間の医療費が一定額を超えた場合は、確定申告で「医療費控除」を申請し、税負担の軽減を図りましょう。そして、お住まいの市区町村が提供する「自治体独自の医療費助成制度」がないかを確認し、利用できるものがあれば積極的に活用してください。
さらに、医療費と介護費の両方が高額になっている場合は、「高額介護合算療養費制度」の申請を忘れないようにしましょう。これらの制度を賢く組み合わせることで、医療費の大幅な削減につながり、安心して生活を送るための大きな助けとなるでしょう。ご自身の状況に合わせて、最適な制度を計画的に活用していくことが大切です。
こちらもおすすめです
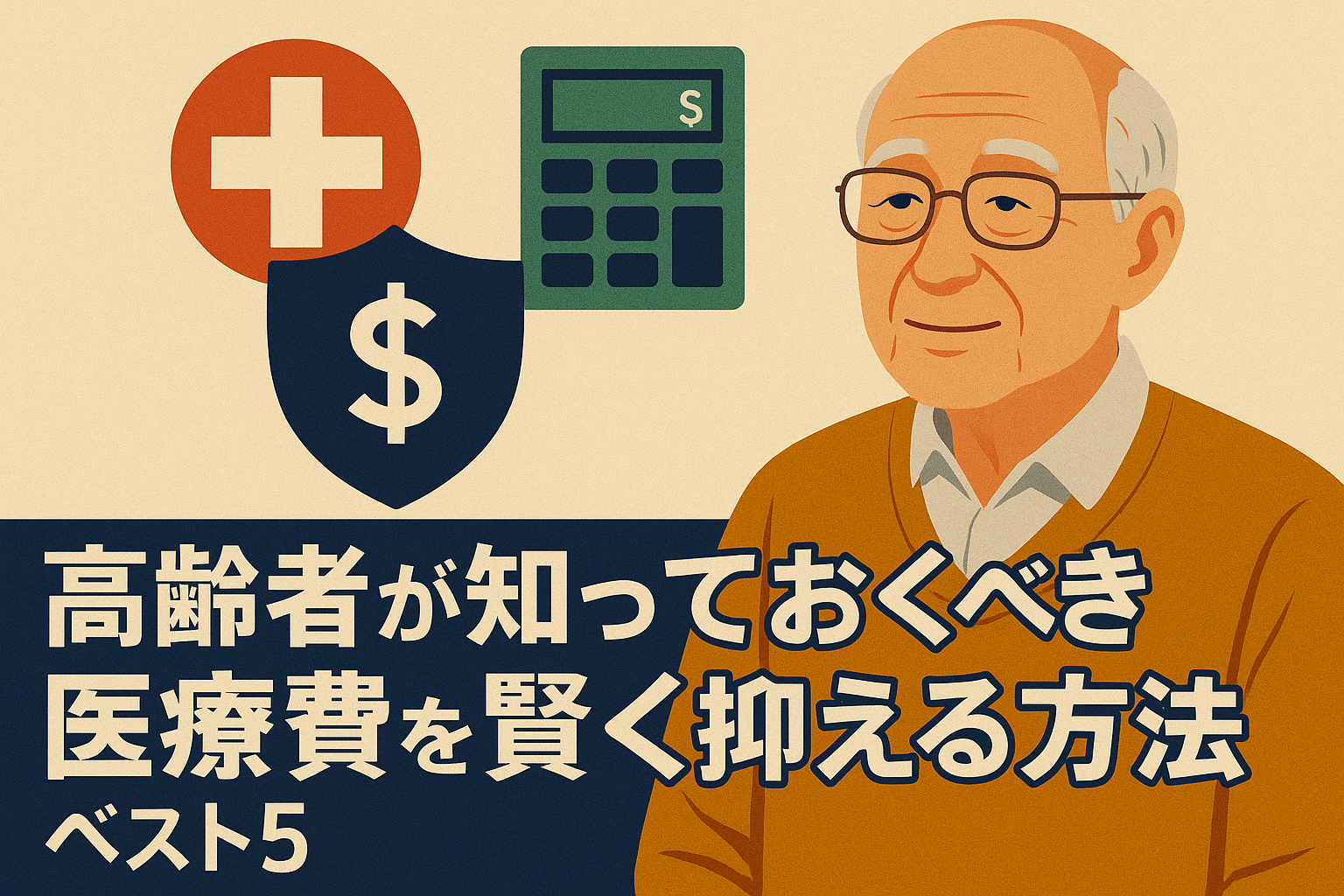
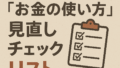
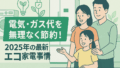
コメント